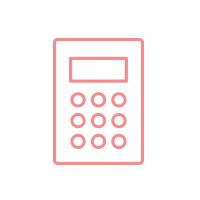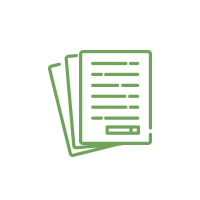タンス預金は相続税対策にならないのか?

タンス預金とは何か
端的に言うと、自宅等に保管している現金のことです。
通常タンスを保管場所に選ぶ人が多いためこう呼びますが、押入れや金庫に保管していてもタンス預金と呼びます。
一般的に現金は、盗難や火災等のリスクを避ける、一定の運用を見込める等の理由から、金融機関に預金等として預ける場合がほとんどです。
しかし、相続発生時に凍結されて自由に使えない、ATM の入出金に手数料がかかる、マイナンバー制度により資産を把握されたくない等の理由からタンス預金をする人が少なからずいます(その残高は、約 60 兆円程度あると言われています。余談ではありますが、過去のデータから、2024 年 7 月の新紙幣発行までタンス預金は一時減少するのではないかとの予測もあります)。
そして次のような質問を受けることがあります。
「タンス預金しておけば税務署にはバレないから、相続税対策になりますよね?」
タンス預金は相続税対策となるのか?
結論から申し上げますと、タンス預金は決して相続税対策とはなりません。
その理由を少し詳しくご説明いたします。
もちろん、先ほど申し上げた金融機関に預けておくことのデメリット等を考慮して、自宅に現金を保管しておくこと自体は、悪いことでも法令違反でもありません。
しかし、そのことにより、盗難・火災のリスクや本人以外が気づかず、相続が発生した後、見つけられないままになってしまうというリスクを考慮しておく必要があります。
そして税に関して言えば、タンス預金であっても、銀行預金や株式等と同じく財産であることには変わりはなく、被相続人の財産である場合は、相続税の課税対象となるということです。
「相続税の課税対象であっても税務署にバレなきゃいいんじゃないの?」と思われている方は要注意です。
なぜかというと、税務署はタンス預金の存在に気づいている可能性が非常に高いのです。
ではどうしてそう言えるのか、国税出身の税理士がその根拠をお話いたします。
国税職員は次のような方法を用いてタンス預金をあぶりだしていきます。
①
国税職員には、適正かつ公平な課税の実現を目的として、国税通則法という法律により「質問検査権」という強い権限が与えられています。
この権限に基づき法令上の手続きを遵守したうえで、金融機関に最大過去10年間の入出金履歴を請求し、被相続人口座からの出金、相続人口座への入金等を詳しく調査します。
必要であれば、金融機関で保管されている届出書類や印鑑票なども確認します。
申告していない金融機関であってもその対象となり得ます。
例えば被相続人口座から大口の出金があったり、複数回の出金があるにも関わらず、それに対応する被相続人口座への入金がない場合などは、相続人等への贈与、他の資産の購入、そして現金のまま自宅等にタンス預金がされているのではないかと疑いを持ち、より深い調査(実地調査)へと移行されていくのです。
②
税務署では、全国の国税局と税務署をネットワークで結ぶシステムを構築し、申告・納税の実績や収集・蓄積された資料情報を一元的に管理しています。
この「国税総合管理システム(KSK)」には、税務署に提出された納税者の申告事績・納税事績はもちろん、税務署に提出された資産の売却・購入などの各種資料や調査の際収集した資料情報も日々蓄積されています。
この蓄積されたデータをさらに丹念に調べていきます。
そこから得た情報を分析した結果、申告が必要であると見込まれるにもかかわらず無申告となっている場合や、申告書が提出されているが、見込まれる課税財産に比べて申告財産が過少であると判断された場合には、実地調査等へ移行し、より細かな調査が行われることになるのです。
③
実地調査となった場合、相続人への聴き取りに加え、通帳や不動産権利証などの財産の現物はもちろん、保管場所として自宅金庫・家具や銀行の貸金庫の中まで確認されます。
この実地調査は、たとえいわゆる「任意調査」であっても受忍義務があるため拒否はできません。
税務署では上記の方法以外にも、様々な方法を駆使して申告漏れ財産の把握に努めていますので、バレないだろうなどと安易に考えることはないようにしましょう。
税務調査の結果、申告されていないタンス預金が発見された場合のペナルティ
税務調査の結果、申告されていないタンス預金が発見され、それが相続財産であると認定された場合はどうなるのでしょうか。
差額分の本税を追加で納付するだけでは済みません。
本税以外に「延滞税」と「加算税」という、適正な申告を行っていれば課されることはなかった税金をペナルティとして課されることになってしまいます。
耳にされたこともあろうかと思いますが、タンス預金を隠すなど悪質性が高いと判断された場合には、「加算税」として「重加算税」(原則として、修正申告等に係る過少申告加算税に代わる場合は本税に対して 35%、期限後申告等に係る無申告加算税に代わる場合は本税に対して 40%の税率となります。が課されてしまいます。
ケースによっては、より重い刑事罰の対象になることもあります。
※こちらの記事については、掲載時点(R6年)における法令等に基づいて作成しております。
その後の法改正等により取扱いが異なっている可能性がありますので、予めご了承をお願いいたします。
最後に

以上のように、タンス預金自体は違法ではなく、デメリットもある反面一定のメリットもあります。
しかし、このタンス預金を相続税の課税財産から除外することは、「脱税」であって「節税」ではありません。しかも税務署に把握される確率も高く、絶対に行ってはならない行為です。
タンス預金などではなく、合法的で適正な「節税」をすることで、税務調査を恐れることなく、より相続税を軽減することができます。
合法的で適正な「節税=相続税対策」は相続税に詳しい税理士に依頼することが肝要です。
当相談室ではこのような相談にも対応しております。
当事務所へのアクセス
泉ヶ丘駅からバス5分!駐車場も完備!
住所:〒599-8253 大阪府堺市中区深阪5-3-31 新和ビル2F
電話番号:0120-290-261
営業時間:平日9:00~18:00 ※ 土・日・祝日、夜間も対応いたします(要予約)