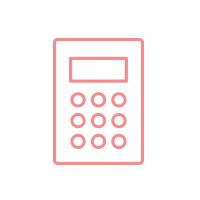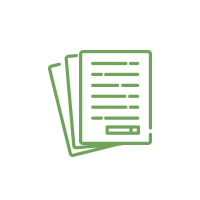遺産分割協議のQ&A
Q1)Q1)父の遺産分割協議が終わった後に、突然「父の子」と名乗る人物が現れました。戸籍を確認したところ、確かに父が認知していた子供でした。この場合、遺産分割協議は最初からやり直す必要があるのでしょうか?
A1)遺産分割協議は、全ての相続人が参加して行われなければ無効となります。そのため、相続人が1人でも欠けていた場合、協議は無効となり、やり直す必要があります。ただし、被相続人が死亡した後に認知された場合や遺言によって認知された場合には、すでに協議が終了していても、その相続分に相当する価額を支払うことで調整が可能です。
Q2)所在不明の相続人がいるため、遺産分割協議を進められません。このような場合は、どう対応すればよいのでしょうか?
A2)行方不明の相続人がいる場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任するための申立てを行います。不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て、不在者の代わりに遺産分割協議に参加することができます。行方不明の期間が長く続いている場合には、「失踪宣告」を受けて、死亡とみなす方法もあります。
Q3)兄弟3人で父の遺産を分けることになりました。私は長男として土地と自宅を相続し、銀行預金2000万円を二男と三男で半分ずつ分けることに合意しています。この場合、遺産分割協議書は作成する必要がありますか?
A3)遺産分割協議書は法律で作成が義務付けられているものではありません。しかし、後々の争いを避けるために、協議内容を明確にし、書面に残しておくことが非常に有用です。また、相続に関する様々な手続きにおいても、遺産分割協議書の提出が求められることがあります。たとえば、不動産の名義変更には必須です。
Q4)実印を持っていないのですが、遺産分割協議書に認印を使用しても問題ありませんか?
A4)認印は使用できません。必ず実印が必要ですので、お住まいの市区町村役場にて印鑑登録を行ってください。なお、登録できる印鑑とできない印鑑がありますので、詳しくは市区町村役場にお問い合わせください。
Q5)海外に住んでいる相続人が実印を持っていません。どうすれば良いでしょうか?
A5)実印の代わりに、その相続人の署名(サイン)を使用します。そして、その国にある日本大使館や日本領事館で、『この署名は本人のものである』と証明してもらう必要があります。国によっては、その国の公証人の証明で十分な場合もありますが、まずはご相談いただくことをお勧めします。
Q6)遺産分割協議書は相続人全員分作成しなければいけませんか?
A6)特に決まったルールはありませんが、通常、相続人の人数分を作成することが推奨されます。1通だけ作ることも可能ですが、例えば銀行での手続きを行う際に、1通を使い回すのは効率的ではありません。
Q7)不動産と借金を長男が相続する内容の遺産分割協議書を作成することは可能ですか?
A7)はい、そのような協議書を作成することは可能です。ただし、借金に関しては注意が必要です。たとえ協議書に『すべての借金は長男が相続する』と記載されていても、債権者(貸主)は法定相続分に基づいて、他の相続人にも返済を求める権利を持っています。そのため、他の相続人が返済した場合、その返済額を長男に請求することが可能です。
Q8)父の遺産を姉と二人で相続しましたが、その後、別の銀行口座に500万円があることが判明しました。この場合、分割協議はやり直しですか?
A8)法定相続分に従って遺産を分割する場合、やり直しの必要はありません。現金や預貯金は法律上、法定相続分に従って分割されます。ただし、遺産分割協議で異なる取り決めが可能です。協議の際には「後に新たな相続財産が判明した場合、その財産は法定相続分に基づいて分割する」という文言を入れておくと便利です。
Q9)父が亡くなり、遺言書が発見されました。しかし、兄弟で話し合った結果、遺言書の内容とは異なる遺産分割を全員で合意しました。この場合、問題はないでしょうか?
A9)遺言書が存在しても、相続人全員の同意が得られれば、遺言書と異なる遺産分割協議を行うことは可能です。ただし、遺言によって特定の相続人に財産が遺贈されている場合、その受遺者の同意も必要です。
Q10)母と弟2人で父の遺産分割協議を済ませた後、父の遺言書が見つかりました。協議内容と遺言書に多少の違いがあるのですが、母と弟も既に協議内容で問題ないと言っています。どうすれば良いでしょうか?
A10) 遺言書は最大限尊重され、法定相続分よりも優先されます。そのため、協議内容と異なる遺言書が発見された場合、通常は遺産分割協議は無効となります。しかし、相続人や受遺者が遺言内容を確認し、それでも協議内容で問題ないと同意すれば、再度の協議は不要です。
Q11)夫が亡くなり、相続人は私と息子です。息子はまだ16歳の未成年者です。母親である私が息子の代理人として遺産分割協議を行うことは可能でしょうか?
A11)法律では、20歳未満の未成年者は行為能力が制限されており、法定代理人の同意がない契約は取り消しが可能です。遺産分割協議も法律行為の一部であり、未成年者が署名
してもそれだけでは不十分です。通常、両親が法定代理人として未成年者の財産管理を行いますが、相続において親も相続人である場合は、利益相反となり、親は子を代理できません。このため、家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらう必要があります。
Q12)夫が交通事故で亡くなり、私は現在2人目の子を妊娠しています。胎児は相続人となり得るでしょうか?また、胎児が相続人である場合、遺産分割はどのように進めるべきですか?
A12)胎児は法律上、相続に関して「既に生まれたもの」として扱われます(民法第886条)。したがって、胎児も相続人としての権利を持ちます。ただし、遺産分割において胎児をどう扱うかは難しい問題です。例えば、胎児が双子であった場合や流産した場合など、後で相続分が変わる可能性があります。そのため、胎児が生まれてくるまでは遺産分割協議を待つのが無難です。
- 相続手続きを放置していませんか?相続手続きを放置するデメリットとは
- 遺産整理業務の内容と流れ
- 相続手続きでつまずくポイントとは?専門家が解説
- 複雑な相続手続きについて ~スムーズに進めるために知っておきたいポイント~
- 相続人が多くて話がまとまらない場合の対処方法
- 面識のない相続人がいる場合
- 相続人が未成年の場合
- 海外に在住している相続人がいる場合の相続手続き
- 相続人が行方不明の場合の手続き方法
- 相続人が認知症の場合の対策
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議の種類とその方法
- 遺産分割協議の注意点
- 遺産分割協議書の作り方
- 遺産分割の調停と審判について
- 遺産分割協議のQ&A
- 遺産分割協議の失敗事例
- 相続に関わる重要な手続き ~スムーズな手続きを行うためのガイド~
- 不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由
- 不動産の名義変更(相続登記)の手続き
- 生命保険金の請求について
- 預貯金の名義変更について
- 株式の名義変更
- 遺族年金の受給
- 相続手続きを放置していませんか?相続手続きを放置するデメリットとは
- 相続の基礎知識
- 法定相続と相続人
- 相続人は誰になるのか
- 養子は相続人になる?
- 前夫が亡くなった時の相続人は?
- 前妻との間に生まれた子供も相続人になる?
- 遺産の分類と相続方法
- 相続手続に必要なもの
- 戸籍収集はこんなに大変!