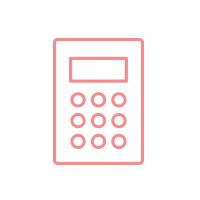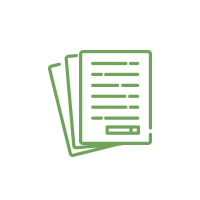遺産分割の調停と審判について
相続財産を分割する際、相続人全員による遺産分割協議で解決することが原則となります。しかし、相続人の中に協議に応じない人がいたり、話し合いがまとまらない場合には、解決策として家庭裁判所の遺産分割調停を利用することになります。
調停手続きの流れ
遺産分割調停では、家庭裁判所の調停委員が相続人同士の意見や主張を丁寧に聞き取りながら進めていきます。この調停の場では、亡くなった人への貢献度、相続人の職業や年齢などを総合的に判断し、相続人全員が納得できるように話し合いを行います。
調停委員の役割
調停委員は、公平な立場から相続人間の調整役を務め、相続人が冷静に話し合いを進められるようサポートします。特に感情的な対立がある場合でも、調停委員が間に入ることでスムーズに話し合いが進みやすくなります。
調停が不成立の場合
残念ながら、話し合いが まとまらず に 調停が不成立 となった場合、 自動的に審判手続 に移行します。
審判手続きの概要
家事審判官(裁判官) が、以下のような 要素 を考慮して審判を行います
- 遺産に属する 物や権利 の 種類・性質
- 各相続人の 年齢・職業・心身の状態
- 生活状況
- その他、一切の 事情 を総合的に判断
これにより、裁判官が 公正な判断 を行い、相続人間の公平を図ることを目指します。
必要な調査
審判では、相続人の主張の正当性を確認するため、相続人や遺産の事実関係を調査することもあります。この段階では、調停よりも専門的・詳細な審理が行われることが多いです。
審判の強制力について
家庭裁判所の審判には強制力があります。相続人が合意できない場合でも、審判の内容に従わなければならないため、法的に 確定した内容として実行されます。
審判に不満がある場合もし審判の内容に不服がある場合には、審判の告知日から2週間以内に即時抗告することが可能です。
家庭裁判所での調停・審判手続きは、感情的な対立が生じやすく、手続きが複雑になりがちです。相続トラブルが起きた際には、専門家のサポートを受けることで、スムーズな解決を目指すことをお勧めします。
- 相続手続きを放置していませんか?相続手続きを放置するデメリットとは
- 遺産整理業務の内容と流れ
- 相続手続きでつまずくポイントとは?専門家が解説
- 複雑な相続手続きについて ~スムーズに進めるために知っておきたいポイント~
- 相続人が多くて話がまとまらない場合の対処方法
- 面識のない相続人がいる場合
- 相続人が未成年の場合
- 海外に在住している相続人がいる場合の相続手続き
- 相続人が行方不明の場合の手続き方法
- 相続人が認知症の場合の対策
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議の種類とその方法
- 遺産分割協議の注意点
- 遺産分割協議書の作り方
- 遺産分割の調停と審判について
- 遺産分割協議のQ&A
- 遺産分割協議の失敗事例
- 相続に関わる重要な手続き ~スムーズな手続きを行うためのガイド~
- 不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由
- 不動産の名義変更(相続登記)の手続き
- 生命保険金の請求について
- 預貯金の名義変更について
- 株式の名義変更
- 遺族年金の受給
- 相続手続きを放置していませんか?相続手続きを放置するデメリットとは
- 相続の基礎知識
- 法定相続と相続人
- 相続人は誰になるのか
- 養子は相続人になる?
- 前夫が亡くなった時の相続人は?
- 前妻との間に生まれた子供も相続人になる?
- 遺産の分類と相続方法
- 相続手続に必要なもの
- 戸籍収集はこんなに大変!