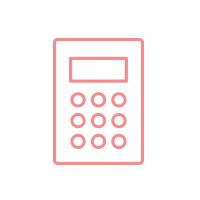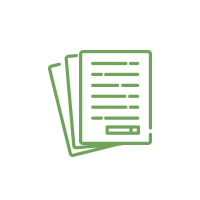遺産分割協議の注意点
遺産分割協議および遺産分割協議書を作成する際には、いくつかの重要な注意点があります。これらを正しく押さえていないと、後々トラブルになる可能性もあるため、以下のポイントをしっかり確認しましょう。
遺産分割協議の注意事項
- 必ず相続人全員で行うことが大前提。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。一堂に会して行う必要はなく、郵送などを利用した持ち回りでの署名・押印も認められています。
- 「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載遺産分割協議書には、誰がどの財産をどれだけ取得するかを 具体的に明記しましょう。
- 後日、発見された遺産に備える協議書を作成する際、万が一後日、追加の遺産(例:借金など)が発見された場合の分配方法 もあらかじめ決めておくと便利です。これにより、再度協議書を作成する手間を省けます。
- 不動産の記載方法:不動産の所在地や面積は登記簿の記載通りに明記します。
- 預貯金の記載方法:預貯金については、銀行名、支店名預金の種類、口座番号などを詳細に記載してください。
- 住所・氏名の記載住民票や印鑑証明書通りに正確に記載することが必要です。
- 実印での押印必ず実印で押印し、印鑑証明書を添付することを忘れずに。
- 協議書が複数ページにわたる場合各ページに契印を行い、正本であることを証明します。
- 協議書の部数を確保する相続人の人数分および金融機関等への提出用として、十分な部数を作成しましょう。
特殊なケースの対応方法
- 相続人が未成年の場合
相続人が未成年の場合は、法定代理人(通常は親権者) が協議に参加するか、未成年者が成年に達するまで待つ 必要があります。
ただし、法定代理人が相続人である場合、互いに利益が対立することになるため、家庭裁判所に特別代理人の選任申立を行う必要があります。
※未成年者が複数いる場合、それぞれ別の特別代理人が必要です。
- 相続人に胎児がいる場合
相続人に胎児がいる場合は、その胎児が生まれてから協議を開始するのが一般的です。
- 推定相続分の譲渡が行われた場合
相続人の一人が遺産分割前に推定相続分の譲渡を行った場合は、その譲り受けた者も協議に参加させなければなりません。
専門家にご相談を
遺産分割協議や 遺産分割協議書の作成方法を誤ると、やり直しになってしまうこともあります。そのため、不安な場合は専門家に相談し、 適切なアドバイスを受けることをお勧めします。当事務所では、経験豊富なスタッフが親切丁寧に対応いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
予約受付専用ダイヤルは0120-290-261になります。
お気軽にご相談ください。
- 相続手続きを放置していませんか?相続手続きを放置するデメリットとは
- 遺産整理業務の内容と流れ
- 相続手続きでつまずくポイントとは?専門家が解説
- 複雑な相続手続きについて ~スムーズに進めるために知っておきたいポイント~
- 相続人が多くて話がまとまらない場合の対処方法
- 面識のない相続人がいる場合
- 相続人が未成年の場合
- 海外に在住している相続人がいる場合の相続手続き
- 相続人が行方不明の場合の手続き方法
- 相続人が認知症の場合の対策
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議の種類とその方法
- 遺産分割協議の注意点
- 遺産分割協議書の作り方
- 遺産分割の調停と審判について
- 遺産分割協議のQ&A
- 遺産分割協議の失敗事例
- 相続に関わる重要な手続き ~スムーズな手続きを行うためのガイド~
- 不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由
- 不動産の名義変更(相続登記)の手続き
- 生命保険金の請求について
- 預貯金の名義変更について
- 株式の名義変更
- 遺族年金の受給
- 相続手続きを放置していませんか?相続手続きを放置するデメリットとは
- 相続の基礎知識
- 法定相続と相続人
- 相続人は誰になるのか
- 養子は相続人になる?
- 前夫が亡くなった時の相続人は?
- 前妻との間に生まれた子供も相続人になる?
- 遺産の分類と相続方法
- 相続手続に必要なもの
- 戸籍収集はこんなに大変!